労働安全衛生法令
労働安全衛生法令
抜粋
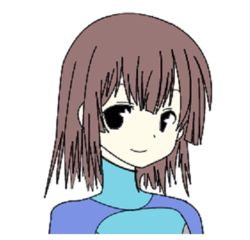
これからは、話と文字だけの勉強が多くなるので、しっかりと目を開けていてね。
あと、(抜粋)とあるのは、いろいろな法律が潜水業務に関係しているけれど、
試験に出題される関係のある部分だけを抜き出しているということだからね。
そして、大事なところは、しっかりと復習してね。

えへへ。汗・・・
眠気覚まし、眠気覚ましっと。
事業者等の責務

まずはじめに、事業者等に定められてる法令からだよ。
法第3条
事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない(以下略)
法第4条
労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するよう努めなければならない。
事業者の講ずべき措置等
法第22条
事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
- 1 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
- 2 放射線、高温、低音、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害(以下略)
譲渡等の制限等
法第42条
特定機械等以外の機械等で、(略)、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等
令第13条
法42条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械とする。
と定められており、「再圧室」、「潜水器」が含まれている。
企画に適合した機械等の使用
規則第27条
事業者は、法別表第2に掲げる機械等及び令13条第3項各号に掲げる機械等については、法第42条の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備したものでなければ使用してはならない。
この中で、よく試験に出題されてるのは、譲渡等の制限等で、「再圧室」、「潜水器」の二つを良く覚えておいてね。

規格又は安全装置を具備しなければ、
譲渡し、貸与し、又は設置してはならないのは、
「再圧室」、「潜水器」の二つですね。
再圧室構造規格(抜粋)
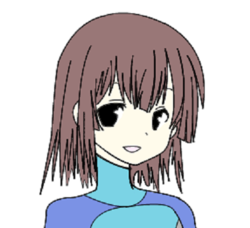
再圧室については、「高気圧障害」の「再圧治療」のところでも勉強したけれど、
この条文から抜き出しされた問題が良く出題されているので、ここも重要だよ。
第1条
再圧室は、副室が設けられているものでなければならない。ただし、可搬型の再圧室にあっては、この限りではない。
第2条
再圧室の主室と副室との間の扉は、それぞれの室を気密に保つことができ、かつ、それぞれの内部の圧力が等しい場合には、容易に開くことができるものでなければならない。
第3条
再圧室の外扉は、当該再圧室の内部の圧力が外部の圧力と等しい場合には、内部及び外部から容易に開くことができるものでなければならない。
第4条
再圧室は、主室及び副室の内部を外部から観察できる窓が設けられているものでなければならない。
第5条
再圧室内の圧力を表示する圧力計は、再圧室への送気及び排気を調節するための弁又はコックを操作する場所に設けられているものでなければならない。
第7条
再圧室は、専用の送気管及び排気管が設けられ、かつ、排気管の先端が開放されているものでなければならない。
第8条
再圧室の床材その他の内装材料及び寝台、寝具その他の器具は不燃性のもの又は難燃性のものでなければならない。
第9条
再圧室の内部の暖房設備は、火気となる恐れのないもの又は高温となって可燃物の点火源となるおそれのないものでなければならない。
第11条
再圧室の内部の電気機械器具は、火花若しくはアークを発し、又は高温となって可燃物の点火源となるおそれのないものでなければならない。
第11条第2項
再圧室の照明器具は、前項の規定によるほか、次に定めるところに適合するものでなければならない。
- 1 再圧室の上部に設け、かつ、直付けしたものであること。
- 2 再圧室の最高使用圧力に耐えるものであること。
- 3 堅固な金属製ガードを取り付けたものであること。
第13条
再圧室は、その内部及び外部に通話装置及び警報装置が設けられ、かつ、その内部の見やすい箇所にこれらの装置の使用方法が掲示されているものでなければならない。
第14条
再圧室は、その内部に、消火のために必要な量の水及び砂を備えているものでなければならない。ただし、その内部及び外部で作動させることができる消火用のさん水装置又は水ホースの設備が内部に設けられている再圧室並びに可搬用の再圧室については、この限りでない。
この条文の中から、正しいものはどれか、間違っているものはどれか、ってよく出題されているよ。
安全衛生教育
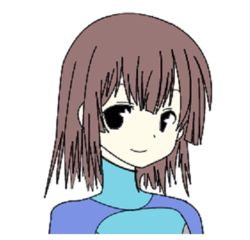
安全衛生教育は、事業者側で必ず行わなければならない事項だよ。
法第59条
事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令でさだめるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
第2項
前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
第3項
事業者は、危険又は有害な業務で厚生労働省が定めるものに(略)当該業務に関する安全又は衛生のための特別な教育を行わなければならない。
雇い入れ時等の教育
規則35条
事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。ただし、(以下略)
特別の教育を必要とする業務
規則第36条
法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は次のとおりとする。
- 第23号 「潜水作業者への送気の調整を行うためのバルブ又はコックを操作する業務」
- 第24号 「再圧室を操作する業務」
特別教育の記録の保存
規則第38条
事業者は、特別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。
特別の教育
高圧則第11条
事業者は、次の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する特別の教育を行わなければならない。
- 第4号 「潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務」
- 第5号 「再圧室を操作する業務」
試験問題によく出題されているのは、「特別の教育」に関する部分が多いよ。

労働者を雇い入れたとき、労働者の作業内容を変更したとき、危険又は有害な業務で厚生労働省が定めるものには、「特別な教育」を行う。
危険又は有害な業務で、潜水業務に関係するものは、
「潜水作業者への送気の調整を行うためのバルブ又はコックを操作する業務」
「再圧室を操作する業務」の二つですね。
特別教育を行なったときは、その記録を3年間保存ですね。
就業制限
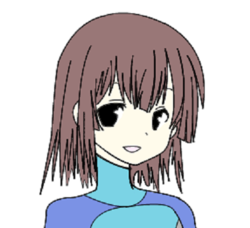
法第61条
事業者は、クレーンの運転その他の業務で政令の定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者(略)厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
第2項
前項の規定により当該業務につくことができる者以外は、当該業務を行ってはならない。
第3項
第1項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他のその資格を証する書面を携帯していなければならない。
第4項
略
就業制限に係る業務
令第20条
法61条第1項で定める業務には次のとおりとする。
- 第9号
「潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務」
就業制限についての資格
規則第41条
法第61条第1項に規定する業務につくことができる者は、別表第3の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ、同表の下欄に掲げる者とする(表略)。
令20条第9号の業務(潜水業務)・・・潜水士免許を受けた者
作業時間の制限
法第65条の4
事業者は、潜水の業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない。
健康診断

法第66条
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。
第2項
事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行わなければならない(略)。
法第66条
第4項
都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、(略)事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を支持することができる。
第5項
労働者は、前各項の規定により事業者が行う健康診断を受けなければならない。(略)
第66条の3
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第66条第1項から第4項及び第5項ただし書き並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。
健康診断を行うべき有害な業務
令第22条
法66条第2項前段の政令で定める有害な業務は、次のとおりとする。
- 第1号 第20条第9号(潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務)に掲げる業務(以下略)
健康診断
高圧則第38条
事業者は、高圧室内業務又は潜水業務に従事する労働者に対し、雇い入れの際、当該業務への配置換えの際及び当該業務についた後6月以内ごとに1回、定期に、次の項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
1 既往歴及び高気圧業務歴の調査
2 関節、腰若しくは下肢の痛み、耳鳴り等の自覚症状又は他覚症状の有無の検査
3 四肢の運動機能の検査
4 鼓膜及び聴力の検査
5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査
6 肺活量の測定
ちなみに、水深に関係なく潜水業務に常時従事する労働者についても、健康診断を行わなければならないよ。
第2項
事業者は、前項の健康診断の結果、医師が必要と認めた者については、次の項目について、医師による健康診断を追加して行わなければならない。
1 作業条件調査
2 肺換気機能検査
3 心電図検査
4 関節部のエックス線直接撮影による検査
健康診断の項目は、「高気圧障害」の「潜水者の健康管理」のところでも少し触れたよね。
健康診断の結果についての医師からの意見聴取
法第66条の4
事業者は、第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書き又は第66条の2の規定による健康診断の結果(異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、(略)、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
健康診断結果の記録の作成
規則第51条
事業者は、(略)、法第66条第4項の規定による指示を受けて行った健康診断、(略)、の結果に基づき、健康診断個人票(様式第五号)を作成して、これを5年間保存しなければならない。
健康診断実施後の措置
法第66条の5
事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、(略)、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条第1項に規定する労働時間等設定改善委員会への報告その他適正な措置を講じなければならない。

事業者は、医師による健康診断を行ない、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対しては、
医師による「特別の項目」についての健康診断を行うのね。
そして、健康診断個人票を5年間記録保存ですね。
潜水業務は特別な項目についての健康診断を行うべき有害な業務に定められているのね。
病者の就業禁止
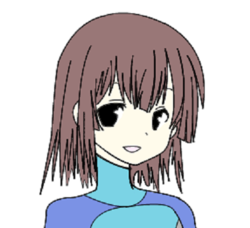
法第68条
事業者は、伝染病の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。
規則第61条
事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。(以下略)
第2項
事業者は、前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見をきかなければならない。
高圧則第41条
事業者は、次の各号のいずれかに掲げる疾病にかかっている労働者については、医師が必要と認める期間、高気圧業務への就業を禁止しなければならない。
1 減圧症その他高気圧による障害又はその後遺症
2 肺結核その他呼吸器の結核又は急性上気道感染、じん肺、肺気腫その他呼吸器系の疾病
3 貧血症、心臓弁膜症、冠状動脈硬化症、高血圧症その他血液又は循環器系の疾病
4 精神神経症、アルコール中毒、神経痛その他精神神経系の疾病
5 メニエール氏病又は中耳炎その他耳管狭さくを伴う耳の疾病
6 関節炎、リウマチスその他運動器の疾病
7 ぜんそく、肥満症、バセドー氏病その他アレルギー性、内分泌系、物質代謝又は栄養の疾病
就業を禁止される病気は、「高気圧障害」の「潜水者の健康管理」のところで勉強したので、再度、復習だよ。
各項目を覚えるのは大変なので、午後からの試験が開始される直前まで、この項目を見ておいて、
問題が配布されたらすぐに、この項目に関する問題が出題されていないかを見て、あったら、最初に解いてしまうと良いかもね。
免許

免許に関することも良く試験に出されるよ。
肝心なのは、試験を受ける受験資格と、
免許証の交付を受けられる年齢は違うことを理解してね。
試験に合格しても、諸条件の規定に該当する場合や一定の年齢までは、
免許が与えられないということだからね。
免許を受けることができる者
法第72条
第12条第1項、第14条又は第61条第1項の免許は、第75条第1項の免許試験に合格した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、免許証を交付して行う。
法第72条第2項
次のいずれかに該当する者には免許を与えない。
- 1 第74条第2項(第3号を除く。)の規定により免許を取り消され、その取り消しの日から起算して1年を経過しない者
- 2 前項に掲げる者のほか、免許の種類に応じて、厚生労働省令で定める者
規則第62条
(略)、又は第61条第1項の免許(以下「免許」という。)を受けることができる者は、別表第4の上欄に掲げる免許の種類に応じて、同表の下欄に掲げる者とする。(表略)
- 潜水士免許・・・・潜水士試験に合格した者
免許の欠陥事由
法第72条第3項
第61条第1項の免許(潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務)については、心身の障害により当該免許にかかる業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものには、同項の免許を与えないことがある。
第4項
都道府県労働局長は、前項の規定により、第61条第1項の免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該免許を申請した者にその旨を通知し、その求めがあったときは、都道府県労働局長の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
高圧則第53条
潜水士免許に係る法第72条第2項第2号の厚生労働省令で定める者は、満18歳に満たない者とする。

心身の障害により当該免許にかかる業務を適正に行うことができない者として定められている者には、
合格しても免許を与えられないこともあるのね。
また、満18歳に満たない者にも与えられないのね。
免許の取消し等
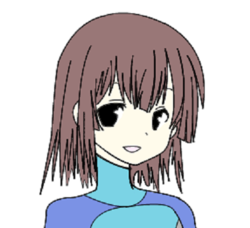
法第74条
都道府県労働局長は、免許を受けた者が第72条第2項第2号に該当するに至ったときは、その免許を取り消さなければならない。
第2項
都道府県労働局長は、免許を受けた者が次の各号のいずかに該当するに至ったときは、その免許を取り消し、又は期間(第1号、第2号、第4号又は第5号に該当する場合にあっては、6月を超えない範囲内の期間)を定めてその免許の効力を停止することができる。
- 第1号 故意又は重大な過失により、当該免許に係る業務について重大な事故を発生させたとき。
- 第2号 当該免許に係る業務について、この法律又はこれに基づく命令
の規定に違反したとき。 - 第3号 当該免許が第61条第1項の免許である場にあっては、第72条第3項(心身の障害等)に規定する厚生労働省令で定める者になったとき。
- 第5号 前各号に掲げる場合のほか、免許の種類に応じて、厚生労働省令で定めるとき。
免許の取消し等
規則第66条
法第74条第2項第5号の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
- 1 免許試験の受験について、不正行為があったとき。
- 2 免許証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。
- 3 免許を受けた者から当該免許の取消しの申請があったとき。

試験に合格し、免許を与えてもらっても、
- 故意又は重大な過失で重大な事故を発生させたとき。
- 潜水業務で法律又は命令の規定に違反したとき。
- 心身の障害等で障害者等に定める者になったとき。
- そのほか、免許の種類に応じて、厚生労働省令で定めるとき。
また、
- 免許試験の受験について、不正行為があったとき。
- 免許証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。
- 免許を受けた者から当該免許の取消しの申請があったとき。
も取消しになるのね。
免許証の交付
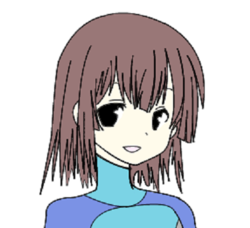
免許証は、最初のころ、「潜水士試験って?」ってところで、少し触れたよね。
規則第66条の2
免許は、免許証(様式第十一号)を交付して行う。(以下略)
免許申請などは「都道府県労働局長」に申請するんだ。
よく「試験センター」とか「労働基準局長」とか、引っ掛け問題も出題されているので注意だよ。
免許の申請手続
規則第66条の3
免許試験に合格した者で、免許を受けようとするもの(次項の者を除く。)は、当該免許試験に合格した後、遅滞なく、免許申請書(様式第12号)を当該免許試験を行つた都道府県労働局長に提出しなければならない。
第2項 以下 略
免許証の再交付又は書替え
規則第67条
免許証の交付を受けた者で、当該免許に係る業務に現に就いているもの又は就こうとするものは、これを滅失し、又は損傷したときは、免許証再交付申請書(様式第12号)を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、免許証の再交付を受けなければならない。
第2項
前項に規定する者は、氏名を変更したときは、免許証書替申請書(様式第12号)を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、免許証の書替えを受けなければならない。
免許の取消しの申請手続
規則第67条の2
免許を受けた者は、当該免許の取消しの申請をしようとするときは、免許取消申請書(様式第13号)を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
免許証の返還
法74条第3項
前項第3号に該当し、同項の規定により免許を取り消された者であっても、その者がその取消しの理由なった事項に該当しなくなったとき、その他、その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。
規則第68条
法第74条の規定により免許の取消しの処分を受けた者は、遅滞なく、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない。

免許の新規申請や、免許証をなくしたり又は損傷したときの再交付、
又は本籍・氏名を変更したときの書替えは、免許証の交付を受けた都道府県労働局長又は住所を管轄する都道府県労働局長に提出するのね。
また、免許を取消してもらうときも同じね。
免許を取り消された者でも、その者がその取消しの理由となった事項に該当しなくなったときや
事情により再び免許を与えるのが適当であると認められたときは、免許を再度もらうことができるのね。
免許証の返還も都道府県労働局長宛ね。
免許試験

免許試験の受験資格などについては、最初のころ、「受験資格は?」でも触れたから、さらっといくよ。
法第75条
免許試験は、厚生労働省令で定める区分ごとに、都道府県労働局長が行う。
規則第69条
法第75条第1項の厚生労働省令で定める免許試験の区分は、次のとおりとする。
- 第16号 潜水士免許試験
第2項
前項の免許試験(以下「免許試験」という。)は、学科試験及び実技試験又はこれらのいずれかによって行う。
第5項
免許試験の受験資格、試験科目及び受験手続並びに教習の受講手続その他免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
受験手続
規則第71条
免許試験を受けようとする者は、免許試験受験申請書(様式第14号)を都道府県労働局長(指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。

はい。
受験資格は、年齢、性別、国籍、学歴、障害の有無には関係がなく、
誰でも受験できるんでしたね。
ただ、免許が与えられるには、一定の制限もあるということですね。
書類の保存・罰則

法第103条
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律又はこれに基づく命令の規定に基づいて作成した書類(次項及び第3項の帳簿を除く。)を、保存しなければならない。
法第119条
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 第1号 第42条(譲渡等の制限)、第59条第3項(安全衛生教育)、第61条第1項(就業制限)、第65条の4(作業時間の制限)、第68条(病者の就業禁止)の規定に違反した者
法第120条
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
- 第1号 第59条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。(安全衛生教育))、第61条第2項(就業制限)、第66条第1項から第3項(健康診断)まで、第66条の3(健康診断の結果の記録)、第66条の6(健康診断の結果の通知)、第103条第1項(書類の保存等)の規定に違反した者

潜水業務に関することで法令で書類を残しなさいと定められている事項はきちんと残さないとならないし、
いろいろ法令等で、定められている事項を守らなければ、罰金などで処分されるということですね。
法令は守らなきゃいけないってことですね。
a:4783 t:1 y:2
